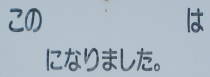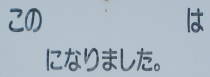【連載】チコちゃんに叱られる! 「ハンコが赤の理由」/ハンコが東アジアだけで習慣化した理由
10月3日(金)に初回放送された表記の番組についての感想・考察。本日は、
- なんでプロ野球の優勝チームがビールかけをするようになったの?
- なぜハンコに使う色は赤色?
- なぜ考えるときに腕を組む?
という3つの話題のうち2.について考察する。
放送では、ハンコに使う色が赤なのは「永遠に残す血の色だから」が正解であると説明された。解説はハンコの歴史に詳しい久米雅雄さん(大阪芸術大学)。
本題に入る前に、この久米さんの肩書きが「大阪芸術大学客員教授 文学博士」というように、「文学博士」をつけて紹介された点が気になった。というのは、この番組に登場する様々な大学教授は、通常は「岡村隆史(○○大学××学部教授)」というように所属先と職名で紹介されており、大概の教授は博士号を持っているはずだがそこまで付け加えることはない。じっさい、今回の話題の1.と3.の解説者も所属先と職名のみで紹介されていた。念のためウィキペディアも参照させていただいたが、別段、学位をつけて紹介しなければならない事情は見当たらなかった。ということで元の話題に戻るが、久米さん&ナレーションによる解説は以下の通り【要約・改変あり】。
- ハンコの色が赤なのは血の色の赤。お墓にまいていた「永遠の赤」
- そもそも初めてハンコが使われていたのはメソポタミア文明のあたり。その頃は粘土が柔らかいうちにそのまま押しつけて跡をうける「スタンプ印章」と、筒状のハンコを粘土の上で転がして跡をける「円筒印章」だった。
- 赤い印が使われた最も古い記述は、調べた中では中国の『北斉書』(636年)にある。この書で赤い印を使ったと書かれている陸法和という人は558年に亡くなっているので、その没年以前からハンコが使われていることが分かる。
- 赤い色に使われていたのは辰砂。
- 辰砂は鮮やかな赤い色をした水銀と硫黄の化合物
- 血に近い赤色をした辰砂は、土に混じっても消えないことから永遠に続く特別な鉱物とされた。
- 辰砂は遺体の周りに撒かれていた。これにより「命が再生される」、「永遠に続く」と信じられていた。
- 採れる地域が限られていて高価なものだったので、貴族階級など地位の高い人だけが使用できた。
- 隋や唐の時代には辰砂は王や限られた権力者しか入手できないものとなり、簡単には偽造されない本物の証しとしてハンコの色に使われていた。
- 日本では7世紀頃に朱で押す印が入ってきた。紀伊半島の里や郡ごとの家の数や税などを記録した帳簿には赤い印が使われていた。
- 奈良・平安時代には土地の支給の公文書などに貴族・役人の印が使用された。
- たくさんの戦国武将が朱印を押した「朱印状」を多用した。放送ではそれらのいくつかが紹介された。
- 江戸時代には商人にも広がり、売買契約やお金の貸し借りの際、辰砂の代用品として安価な酸化鉄が使われた。
- 明治4年に印鑑登録制度が導入され、全国に広がった。
- 「ハンコの色は赤色でなければならない」という法律は無いが、今も赤が使い続けられている。
- 【補足】現代の朱肉の多くは酸化鉄系の無機顔料を使用し長い間残りやすいため赤がオススメ。
ここからは私の感想・考察を述べる。
まず「赤いハンコ」の件だが、かつて貴重な辰砂が使われ偽造されにくかったという説明部分は今の時代とは直接結びつかないように思う。そんなに難しく考えず、単に、「普通の文書は白い紙に黒字で印刷されているので、判の色は赤色(朱色)であるのがいちばん目立ちやすい」と考えればそれでよいのではないかと思う。赤色であれば押印洩れにも気づきやすいし、文書全体が何かの約束事の文書であると気づきやすいことで誤って廃棄されにくくなる。
私自身は以前からハンコにどれほどの認証機能があるのか疑問に思っていた。
- どんなに複雑で精密なハンコがあったとしてもそれが本人が押したものであるという証拠にはならない。
- 例えば戦国武将がどんなに精密なハンコを作ったからといって、それを受け取った人が本物のハンコの印影を知らなければ、偽物との区別ができない。
- 印鑑証明のシステムがあってもスキャナで印影を読み込み3Dプリンターで複製を作れば簡単に偽造できる。
現職時代、さまざまな事務文書にハンコを押す必要があったが、事務室に書類を提出した時に押印洩れが指摘され研究室までハンコを取りに行くことがしばしばあった。本人が目の前にいるのだからハンコ無しでもエエじゃないかと思うのだが、当時の規則上、三文判でも何でもハンコを押すことが義務づけられていた。
最近では殆どの文書は印鑑無しで提出したり、受領したりできるようになっていてありがたい。すでに行われているが、指紋認証や顔認証があれば、もはやハンコが出る幕は無い。
ウィキペディアによれば、
しばしば世間一般では、正式には印章と呼ばれるもののことをハンコ、印鑑(いんかん)と呼んでいるが、厳密には印章あるいはハンコと同じ意味で「印鑑」という語を用いるのは正確ではない。古くは、印影と印章の所有者(押印した者)を一致させるために、印章を登録させた。この印影の登録簿を指して「印鑑」と呼んだ。転じて、日本では印鑑登録に用いた印章(実印)を特に印鑑と呼ぶこともあり、更には銀行印などの登録印や、印章全般もそのように呼ぶ場合もある。
と記されており、「印鑑」と「ハンコ」は区別しておいたほうが良さそうだ。
ところで現在、ハンコが使われている国・地域は東アジアだけに限られているように思われる。その理由をChatGPTに尋ねたところ、以下のような回答をいただいた。
とても良いご質問です。
確かに「ハンコ(印章)」を社会制度として今も日常的に使っているのは、現在では **日本・中国・韓国・台湾など東アジア圏**にほぼ限られています。
この地域だけで印章文化が根強く残っている理由は、歴史的・文化的・社会的な背景が複合的に関係しています。以下のように整理できます。
- 印章文化の「起点」が東アジアにあった
印章は世界の各地で古代から存在しましたが、**東アジアでは特に早い段階で国家制度に組み込まれた**ことが大きな特徴です。
* 中国では紀元前から「印章(いんしょう)」が行政・法的証明の手段として使われ、皇帝から役人に与えられる「印」が官位そのものの象徴でした。
* この制度が**漢字文化圏**を通じて朝鮮・日本・ベトナムへ伝わり、「文書に印を押して公的な意味を与える」という観念が広まりました。→ つまり、東アジアでは印章が「個人署名」よりも先に公的証明の手段として確立したのです。
- 文字文化との親和性(漢字文化との関係)
* 東アジアでは、もともと「署名」という概念よりも、**印章=権威・証明の象徴**として発展しました。
漢字は「書く人によって字形が変わる」ため、筆跡による個人認証は西欧のアルファベットより難しかったのです。
→ そのため、**一定の形を持つ刻印**のほうが信頼されました。
- 書記官僚社会の形成
* 中国や日本では、古代から中央集権的な官僚制が発達しました。
書面による命令・通達・契約などが日常的に行われ、その正当性を保証するために印章が不可欠でした。
* 一方ヨーロッパでは、封蝋や署名が主流で、封建制・個人責任の概念と結びついて発展しました。
- 西欧化の過程での分岐
* 19世紀以降、西欧諸国では署名やサイン文化が定着し、印章は貴族的な儀礼用途に限られるようになります。
* 東アジア諸国も近代化の中で署名制度を導入しましたが、**既存の印章文化との整合性を取る形で両立**しました。
その結果、印鑑証明制度などが行政・法体系に組み込まれ、簡単には廃止できなくなりました。
- 社会的・心理的な要因
* ハンコには「形式」「礼儀」「確実さ」を重んじる東アジア的な文化価値があり、**「印を押す=正式・責任を持つ」**という儀式性が社会的信頼を支える役割を果たしてきました。
* 署名よりも「印を押す」ほうが「約束・契約の重み」を感じやすい、という心理的側面もあります。
- 現在の状況
- 中国:実印・公印は依然として法的効力が強いが、電子印章やデジタル署名の普及も進行中。
- 韓国:印鑑登録制度がありつつも、電子署名・生体認証が広く利用されている。
- 日本:行政手続のデジタル化に伴い、徐々に「脱ハンコ」が進行中。
- 台湾:公的手続きではまだ印章を使用する場面が多い。
→ 歴史的には同じ源流を持ちながら、**近年は急速に西欧型の署名・デジタル署名へ移行**しつつあります。
- ### まとめ
| 観点 | 東アジアで残った理由 |
| ---- | ------------------ |
| 歴史 | 中国古代からの制度的伝統 |
| 文化 | 漢字文化との親和性、形式重視の価値観 |
| 社会制度 | 官僚制・印鑑登録制度などの定着 |
| 心理 | 印を押す行為の「儀式性」「信頼性」 |
| 技術 | デジタル化により急速に変化中 |
ChatGPTにはさらに、「なぜヨーロッパでは署名文化が発展し、印章文化が残らなかったのか」を、東アジアとの対比で説明してもらった。
- 起源の違い:個人の署名 vs 国家の印章
- ### ● ヨーロッパ
* 西洋でも中世以前から「印章(seal)」は存在しました。
封蝋(シーリングワックス)に指輪の刻印(シグネットリング)を押す習慣が貴族・聖職者の間にありました。
* しかしそれは「**個人の所有物=その人の意志の象徴**」として用いられたもので、**国家や官僚制度の正式印**としてではなく、私的・人格的な署名の延長線上にありました。
→ つまり、ヨーロッパでは「印章=個人の印」と「署名=個人の責任表示」が早くから結びついていたのです。
- ### ● 東アジア
* 対して中国では「印章=皇帝・官僚の権威の象徴」であり、署名よりも先に「国家の公式証明」として成立しました。
* 印章の使用は個人の責任よりも、「官(お上)の権威を保証する印」として広まったのです。
- 文字体系の違い:筆跡が「署名」になりやすかった
* ヨーロッパの**アルファベット**は、比較的単純な形で、個人の筆跡の特徴が出やすい文字体系です。
* 中世以降、「**自分で書いた名前=本人の証明**」という文化が成立しました。
* また、キリスト教文化では**聖書を「自筆で誓う」**という概念があり、署名に「誓約」「信義」の意味が付随しました。
→ 署名は「本人が誓って書いた証拠」であり、宗教的にも倫理的にも重みを持つ行為となりました。
- 社会構造の違い:個人責任社会 vs 官僚主義社会
* ヨーロッパは封建制社会であり、個人(貴族・騎士など)がそれぞれの責任で契約を結ぶ社会でした。
したがって、「**本人の署名こそが契約の証明**」となります。
* 一方、東アジアは官僚的・中央集権的な体制の下、国家・組織が発行する印が正しい」とされる**権威主義的な文書文化**が支配的でした。
→ つまり、ヨーロッパでは「署名=個人責任」、東アジアでは「印章=公的権威」という役割分担が生まれたのです。
- 印章が衰退した理由(ヨーロッパ)
印章文化は中世にはまだ生きていましたが、近代に入ると次第に廃れていきます。
| 時期 | 理由 |
| ------- | -------------------------- |
| 15?16世紀 | ルネサンス期に文字教育が普及し、署名能力が広まる |
| 17?18世紀 | 近代法の発達により、「署名=法的効力」と明文化される |
| 19世紀以降 | 封蝋や指輪印章は儀礼的・装飾的用途に限定される |
→ 「署名」のほうが「個人の意志を直接示す」として信頼されるようになりました。
- 近代法制度の違い:証明の中心が異なる
| 項目 | 東アジア | ヨーロッパ |
| ------ | ------------ | --------- |
| 文書の真正性 | 公的印章で保証 | 本人の署名で保証 |
| 基本概念 | 「印=権威の証」 | 「署名=意志の証」 |
| 契約文化 | 官製・制度的 | 個人・人格的 |
| 現代の流れ | 印鑑登録+電子署名の共存 | 署名+電子署名のみ |
- 心理的・文化的な違いも大きい
* 東アジアでは「印を押す」行為に儀式的な重みがあり、形式が重んじられる。
* ヨーロッパでは「自分の手で名前を書く」ことが個人の誠実さ・責任の表れ。
* よって、**どちらの文化も「信頼の証」**ではあるが、その「信頼の表現方法」が異なってきたわけです。
- ### ? まとめ:東アジアに印章が残り、ヨーロッパで署名が根付いた理由
| 要因 | 東アジア(印章文化) | ヨーロッパ(署名文化) |
| ------ | ------------ | ---------------- |
| 歴史的出発点 | 国家・官僚制度の印章 | 個人・宗教的誓約の署名 |
| 文字体系 | 漢字(筆跡識別が難しい) | アルファベット(筆跡識別が容易) |
| 社会構造 | 集団主義・官僚主義 | 個人主義・契約社会 |
| 信頼の基準 | 権威による保証 | 個人の意志・責任 |
| 現代の姿 | 印鑑制度+電子印章 | 署名制度+電子署名 |
上記の説明で「ヨーロッパのアルファベットは、比較的単純な形で、個人の筆跡の特徴が出やすい文字体系です。」とあったが、別段、漢字でもハングルでも個人の筆跡の特徴は出やすいように思う。
次回に続く。
|