|
※クリックで全体表示。 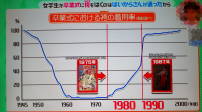
|
2月21日初回放送の『チコちゃんに叱られる!』で取り上げられた袴の話題。女子学生が卒業式に袴をはく比率は1945年から1960年にかけて急低下しほぼゼロの状態が続いた。その後1980年代前半から上昇に転じ最近ではほぼ100%に復活した。【都内の女子大学の卒業アルバムをもとに番組が調べたデータに基づく】。↓の記事参照。 |
じぶん更新日記1997年5月6日開設Copyright(C)長谷川芳典 |
|
※クリックで全体表示。 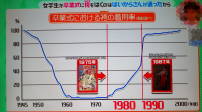
|
2月21日初回放送の『チコちゃんに叱られる!』で取り上げられた袴の話題。女子学生が卒業式に袴をはく比率は1945年から1960年にかけて急低下しほぼゼロの状態が続いた。その後1980年代前半から上昇に転じ最近ではほぼ100%に復活した。【都内の女子大学の卒業アルバムをもとに番組が調べたデータに基づく】。↓の記事参照。 |
【連載】チコちゃんに叱られる! 「女学生が卒業式に袴をはく理由は、はいからさんが通ったから?」 2月21日(金)に初回放送された表記の番組についての感想・考察。この日は、
さて1.の袴の話題であるが、この疑問は、くるみ(5さい)さんからの質問: ●大学や専門学校の卒業式において女性はなぜはかまを着るのですか に答えるという設定であったが、5歳の子どもにしては、使う言葉や漢字、文体が大人すぎる。何かのヤラセではないだろうか。 それはそれとして、放送では「はいからさんが通ったから」が正解であると説明された。着物の歴史や流行を研究している田中淑江さん(共立女子大学)&ナレーションによる解説は以下の通り【要約・改変あり】。
アイスクリームの売上と溺死の相関関係: アイスクリームの売上が増えると溺死の数が増えるという相関関係が見られることがあります。しかし、これは因果関係を示しているわけではありません。むしろ、共通の原因である暑い天候が両方の現象に影響を与えています。暑い夏の日には、アイスクリームの売上が増えるのと同時に、多くの人が水辺に行くことが増え、それに伴って溺死のリスクも高まるのです。ま、『はいからさんが通る』と卒業式の衣装についてはいずれも袴に関するものなので、アイスクリームと溺死に比べれば因果関係が高いと言えるかもしれない。ちなみに、ウィキペディアによれば、
もっとも、いくら人気が出ていたとしても、1つの漫画作品や映画だけで大学生の服装が変わってしまうというのはにわかには信じがたい。例えば嗚呼!!花の応援団の漫画や映画も人気があったが、だからといって当時の大学生がみんな応援団の格好をするようになったわけではあるまい。 ちなみに『はいからさんが通る』が連載された1975年〜1977年と言えばちょうど私が学部卒業(1975年)と大学院修士課程修了(1977年)の年に重なっている。もっともその頃、卒業式の服装がどんなものであったのかは殆ど記憶に残っていない。但し、学生運動が下火となったことで、いくぶん華やかな服装が出てきたような気もする。もっともこちらやこちらにあるような派手なコスプレを見かけることはなかった【Copilotに尋ねたところでは、少なくとも2017年頃からであったという】。 女学生の袴着用に『はいからさんが通る』が影響を与えたことが確かであったとしても、それはおそらくキッカケの1つに過ぎないように思う。 おそらく一番の理由は「みんなに合わせる」ということにある。100人の卒業生のうち99人が袴を着用するようになった時、洋服で参加するというのはかなり目立つし勇気のいることだ。もちろん上にリンクしたように自分だけ目立つようなコスプレを楽しむ卒業生も皆無とは言えないが、たいがいは奇を衒うことを避けようとする。じっさい、袴と洋服が50%ずつであれば均衡が保たれるが、袴が70%、80%というように多数派を形成すると加速度的に多数派の比率が上昇する。 2番目に考えられるのは、大学生協が袴の着用をサポートするようになったことである。【こちらの案内参照】 岡大生協の施設入り口にも、卒業式の相当前から袴の見本が展示され予約を受け付けるようになっている。 もちろん、最大の理由は、人生で1回くらい袴姿になってみたいという本人の願望にあるとは思う。振り袖やウェディングドレスと異なり、大勢の人が集まる場所で袴姿を披露できるのは卒業式の場だけである。多少お金がかかってもせっかくの機会を逃すまいと考えている人は少なくないだろう。 ということで、私の考えは以下のようにまとめられる。 ●卒業式に袴を着用する女学生が増えたのは、『はいからさんが通る』などの影響で袴の魅力が再認識され、人生一度の思い出として卒業式に袴を着用する人が一定比率に増加したのがキッカケ。これにより袴のレンタルビジネスが確立し、大学生協との連携もあって、安価かつ便利に着用できるようになり着用率が急上昇し多数派を形成。これにより「周りに合わせる」という消極的理由から袴を着用する人も出てきて、圧倒的多数を占めるに至った。 なお、卒業式の日に紋付き袴を着用する男子学生も一定数見かけることがあるが、昨年の岡大の卒業式などの動画を見る限りは多数派とは言いがたい。 ●卒業式に袴をはく女子学生が多いのに対して、なぜ男子学生の多くは袴をはかないのか? ということも説明する必要があるように思う【男性版の『はいからさんが通る』の漫画や映画が無かったからなのか?】 次回に続く。 |