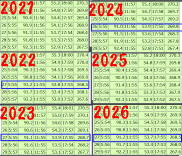【連載】チコちゃんに叱られる! 「船に名前がつけられる理由」 /船に「丸」がつけられる理由と「船艦大和」や南極観測船に「丸」がつけられなかった理由
9月26日(金)に初回放送された表記の番組についての感想・考察。この日の話題は以下の通り。
- なんで船には名前がついているの?
- なんでベルトを締めるようになった?
- なんで貴様って失礼な言葉なの?
本日はこのうち1.について考察する。
さて、放送内容とは前後するが、船に名前がついている理由については以下のように分けて考える必要がある。
- 日本の領海の外まで航行する船
- 領海内だけで航行する船
後述するように、1.については省令で義務づけられているいっぽう、2.については法律上は名前をつけなくてもよいという。なので、今回の放送では、
●日本の領海内しか航行しない漁船や国内フェリーは、名前をつけなくてもいいはずなのになぜ名前をつけているのか?
についての説明ということになる。
放送では「名前がないと安全祈願ができないから」が正解であるとされた。名前の歴史などの研究をしている大形徹さん(立命館大学)&ナレーションによる解説は以下の通り【要約・改変あり】。
- 車、電車、飛行機など世の中にはたくさんの乗り物があるが、識別番号のようなものではなく、愛称のような名前が1つ1つつけられているのは船だけ。
- 車はナンバープレートのみ。
- 新幹線は「のぞみ47号」というように車両の種類と列車番号はあるが1つ1つに名前がつけられているわけではない。
- 船に名前をつけることは国土交通省の省令で決められている。
- 「小型船舶登録規則」では「第二十五条 日本船舶である小型船舶の所有者は、国土交通大臣から有効な国籍証明書(当該船舶が日本船舶であることを証明する書面をいう。以下同じ。)の交付を受け、これを当該船舶内に備え置き、かつ、国土交通省令で定めるところにより船名を表示しなければ、当該船舶を国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事させてはならない。」と定められている。
- 要するに、日本の領海外に出るすべての船は船のパスポートを発行するから船に名前を書いておいてね、ということ。
- なので、名前をつけなければならないのは領海外に出る船だけ。
- なので領海外に出ない船には名前をつける義務はないが、日本では伝統的に名前をつけることが根付いている。
- 名前がつけられた最も古い船としては4世紀頃、応神天皇が「伊豆の国守に船を造らせる...『枯野(からの)』と名づけたり」という記述が『日本書紀』(720年)にある。
- 船に名前をつけたのは大自然に対する怖れから。昔の人にとって海はとても恐ろしい存在だった。そこで航海中の安全を神様にお願いしたが、名前が無いと安全祈願ができないので、船を識別するために名前がつけられた。
放送では続いて、船の名前に「丸」がつけられていることが多い理由について解説された。
- 発祥については諸説ある。
- 「丸」愛称説
坂上田村麻呂などの「麻呂」が「丸」にかわり、人以外の大切なものにも使用された
- 「丸」お城説
城の「本丸」など
- 大形さん推奨の「汚い」を意味する「丸」説
- 日本の古い言葉で「まる」という動詞には「排泄する」という意味があり、「おまる」の由来になっている。
- 日本では古くから汚れたものには悪霊も近づかないと考えられていた。
- 船に「丸」をつければ悪霊が寄ってこないという魔除けになった。
- 源義経の幼名である牛若丸のように幼名に丸がつけられていたのも、子どもに悪霊が憑かないためだった、とされている。
- 理由は不明だが、1900年にできた『船舶法取扱手続』には、
●船舶ノ名称ニハ...成ヘク其ノ末尾ニ丸ノ文字を附セシムヘシ
という記述がある。但しこの条文は2001年に削除され、今は船の名前は自由につけてよいことになっている。
ここからは私の感想・考察を述べる。
まず、解説の「新幹線は「のぞみ47号」というように車両の種類と列車番号はあるが1つ1つに名前がつけられているわけではない。」という部分であるが、私が子どもの頃は、国鉄の寝台特急の『富士』や『さくら』など、日本海縦貫の『白鳥』や『きたぐに』などの愛称がつけられており、憧れの的だった。今でも寝台特急の『サンライズ瀬戸』とか津山線の観光列車『SAKU美SAKU楽』などの愛称が親しまれている。
いっぽう飛行機は直近で搭乗した『GA-880便』のように便名のみで呼ばれている。この便ではたまたまピカチュウが描かれた機材が使われていたが、搭乗時に特に感動したわけでもなかった。
念のためChatGPTに「船舶に名前がつけられているのはなぜですか?」と尋ねたところ、以下のような回答をいただいた。
いい質問です。
船舶に名前がつけられている理由には、いくつかの歴史的・実務的な背景があります。
- **識別のため**
- 船は世界中を航行しますので、他の船と区別する必要があります。
- 名前(船名)は国際的に登録され、船舶番号や船籍港とともに「その船が何者か」を示す基本情報になります。
- たとえば「○○丸」や「Queen Mary 2」といった船名は、同じ造船所の姉妹船や同型船でも一目で区別できる役割を果たします。
- **安全・通信上の理由**
- 無線通信や港湾での手続きでは、船名を名乗ることでスムーズに連絡が取れます。
- 船体に大きく書かれた船名は、目視確認にも役立ちます。
- **伝統・文化的な理由**
- 古代から船は「乗員の命を預ける存在」であり、人格を与えるように名前を付けて大切に扱われてきました。
- 船に女性名や神話の人物名を付ける慣習は、古代ギリシャやローマ時代に遡ります。
- 日本でも「○○丸」と名付ける伝統があり、「丸」は「円満」「守られる」といった意味を持つといわれます。
- **記念や象徴**
- 船主、出資者、地域、歴史上の人物、希望する未来などを象徴して名付けられることが多いです。
- たとえば客船や軍艦には国威を示す名前が、貨物船には所有会社や系列のテーマに沿った名前が付けられます。
つまり **実務上の識別** と **文化的な信仰・伝統** が結びついて、船には必ず名前が付けられるようになっているのです。
続いて「なぜ日本では特に『丸』が多いのか」についても解説してもらった。
承知しました。「船名に『丸』が多い理由」について整理してご説明しますね。
## 日本の船名と「丸」の由来
- **船を守るという意味合い**
- 「丸」には「円満」「完全」「守られている」というニュアンスがあり、航海の安全祈願として付けられました。
- 船を擬人化して「この船がまるごと無事に帰ってきますように」と願う意味を込めたともいわれます。
- **室町〜江戸時代に広まった慣習**
- 室町時代の軍船や大名の船の名前に「丸」が使われ始めたとされます。
- 江戸時代になると、幕府の御用船や商船に「○○丸」と名づけるのが一般化しました。
- 「日本丸」「宝船丸」などは吉祥的な響きもあり、商売繁盛や航海成功を願う文化と結びついていきます。
- **城の「丸」との関連説**
- 江戸城などの城郭には「本丸」「二の丸」といった区画があります。
- これは「防御の輪」を意味しており、船名における「丸」も「船を守る砦」という感覚から来ていると考える説があります。
- **武士的な影響**
- 戦国期に武将が自らの「旗印」や「馬」に縁起を担いだのと同じように、船にも縁起を込めた名前を付けました。
- 武士が所有する軍船にも「丸」が多く用いられ、その流れが庶民や商人の船にも広がったとされます。
- **近代以降の継承**
- 明治時代に西洋式の船が導入されても、日本の船主や海運会社は伝統を重んじ、「○○丸」を好んで使用しました。
- 有名な練習帆船「日本丸」「海王丸」もその流れを受け継いでいます。
- ## まとめ
「丸」が使われるのは単なる慣習ではなく、
- **安全祈願(円満・守護)**
- **歴史的慣行(江戸期の御用船・商船)**
- **城郭や武士文化との連想**
といった要素が組み合わさって根付いた日本独自の船名文化です。
ということでChatGPTの回答では、今回の放送の「まる→汚い→魔除け」には言及されなかった。
ところで「船艦大和」で知られるように、旧日本軍や自衛隊の船には「丸」はつけられていない。この点についてもChatGPTに尋ねたところ、以下のような回答をいただいた。
承知しました。「戦艦 *大和* に『大和丸』という名前が絶対につけられなかった理由」を掘り下げてご説明します。
- **軍艦は国家の象徴、商船とは一線を画す**
- 「丸」は本来、**商船や漁船、民間船の呼称**です。
- 軍艦は「国家の威信」「国防の象徴」であり、商船と同じ命名法では格式が不足するとみなされました。
- 特に *大和* は「日本そのもの」を象徴する国名であり、国家最高の戦艦に「丸」を付けるのは不似合いとされました。
- **帝国海軍の命名規則**
* 明治期以降、軍艦名は厳格に規則化されました。
- 戦艦・巡洋戦艦 → **旧国名**(大和、武蔵、長門、伊勢 など)
- 巡洋艦 → **山や川の名前**
- 駆逐艦 → **天候・自然現象**
- 潜水艦 → **数字(伊〇〇、呂〇〇)**
この規則の中に「丸」は一切含まれていません。
もし「大和丸」と名づけると、軍艦の公式な体系から逸脱し、**軍艦として認められない** ほど不自然になります。
- **「守られる船」と「守る船」の思想的違い**
- 「丸」には「円満」「守られる」「無事に帰る」といった意味があり、民間の航海安全祈願に適していました。
- しかし戦艦は **「国家を守るために存在する攻撃力の象徴」** です。
- その役割からすれば、「丸」はむしろ受動的で弱々しい印象になり、戦艦の精神性にそぐわないと考えられました。
- **西洋海軍の伝統の影響**
- 日本は近代海軍を築く際にイギリスを手本にしました。
- 英国海軍の戦艦には「Victory」「Dreadnought」「Royal Sovereign」など威厳ある名が使われ、縁起担ぎの呼称はありません。
- もし「大和丸」としてしまえば、西洋列強の軍艦と並んだときに **「商船」や「練習船」のように見られてしまう** 恐れがありました。
- **「大和」は特別中の特別だった**
- 「大和」は日本の古称であり、国家そのものを象徴する名前です。
- 日本海軍の最高戦艦にその名を与えるのは「国の魂を託す」意味がありました。
- そこに「丸」をつけると、むしろ **神聖さ・威厳が薄れ、商船的・庶民的に見えてしまう** ため、決して許されなかったのです。
- ## まとめ
戦艦 *大和* が「大和丸」となりえなかったのは、
- 軍艦と商船の明確な区別
- 帝国海軍の命名規則
- 「守られる船」と「守る船」の思想的違い
- 西洋海軍の影響
- そして「大和」という名の特別性
がすべて重なっていたからです。
最後に、南極観測船の名前に「丸」がつけられなかった理由も尋ねてみた。
はい、とても良い視点です。
南極観測船(「宗谷」「ふじ」「しらせ」など)に「丸」がつけられなかったのも、基本的には **軍艦と同じ理由** によるものです。ただし背景には少し複雑な事情があります。
- **「宗谷」はもともと軍艦(特務艦)**
- 初代「宗谷」は、建造時はソ連向け貨物船、その後日本海軍に接収され「特務艦 宗谷」として使用されました。
- 戦後は海上保安庁 → 海上自衛隊に引き継がれ、南極観測船になりました。
- もともと **軍艦として命名された時点で「丸」は使われていない** ため、そのまま観測船としても「宗谷」のまま運用されたわけです。
- **「しらせ」「ふじ」など後継艦も軍艦命名ルールを踏襲**
- 2代目以降の観測船は建造時から「観測船」として作られましたが、所管が海上自衛隊であり、命名は **軍艦に準じた規則** が適用されました。
- 「ふじ」=山岳名
- 「しらせ」=探検家「白瀬矗(しらせ のぶ)」の姓
- つまり軍艦と同様に、「丸」は使わないのが自然な流れでした。
- **「丸」は“私的船・商船”の呼称**
- 南極観測船は国家プロジェクトの一部であり、**国家の任務を担う公的船舶** です。
- 「丸」は民間船に多く使われるため、公的威信を示す船には避けられました。
- **命名の象徴性**
- 観測船の名は単なる船名ではなく「日本の科学探検の象徴」でした。
- そのため「富士山」や「偉大な探検家の名」など、国際的に誇れる名前が選ばれ、縁起担ぎの「丸」は不採用となったのです。
- ## まとめ
南極観測船に「丸」が付かなかった理由は、
- 初代「宗谷」が軍艦由来で「丸」を持たなかった
- 後継艦も海自の管轄下で軍艦式命名ルールに従った
- 公的・象徴的役割を重視して、商船風の「丸」を避けた
という流れにあります。
次回に続く。
|