|
※クリックで全体表示。 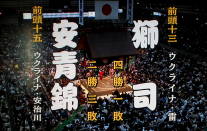
|
大相撲三月場所(春場所)6日目、ウクライナ出身の獅子と安青錦が幕内で初めて対戦した。こちらによれば、大相撲ではこれまでに16カ国・地域の計76人の関取が誕生しており、幕内で初めて同じ国同士の力士が対戦したのは平成3年春場所、米国出身の大関小錦と小結曙だった。以来、モンゴル、ロシア、ジョージア、ブルガリア同士の対戦があり、今回は6カ国目になるという。 ついでながら、6日目(3月14日)終了時点での私の優勝予想は以下の通り。
|
じぶん更新日記1997年5月6日開設Copyright(C)長谷川芳典 |
|
※クリックで全体表示。 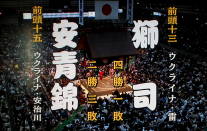
|
大相撲三月場所(春場所)6日目、ウクライナ出身の獅子と安青錦が幕内で初めて対戦した。こちらによれば、大相撲ではこれまでに16カ国・地域の計76人の関取が誕生しており、幕内で初めて同じ国同士の力士が対戦したのは平成3年春場所、米国出身の大関小錦と小結曙だった。以来、モンゴル、ロシア、ジョージア、ブルガリア同士の対戦があり、今回は6カ国目になるという。 ついでながら、6日目(3月14日)終了時点での私の優勝予想は以下の通り。
|
【連載】最近視聴したYouTube動画(23)岡田斗司夫さんの動画をもとに宗教について考察する(22)神道(2)素朴な疑問4つ 昨日に続いて、宗教についての考察。岡田さんの動画からは離れるが、本日はその最終回として、神道についての素朴な疑問と、ウィキペディアなどで調べた限りの回答をまとめておく。私の疑問は以下の通り。
まず、1.についてはCopilotに尋ねたところ以下のような回答をいただいた【要約・改変あり】。 神道には、複数の宗派があり、それぞれに独自の特徴や伝統があります。神道は古代日本の伝統的な宗教であり、明確な「宗派」というよりも、地域や家族、時代ごとにさまざまな慣習や信仰が発展してきました。しかし、明治時代には、政府が国家神道を形成し、それとは区別される宗派が生まれました。以下は主な神道の宗派です: 神道の元締めというと神社本庁が思い浮かぶが、神社本庁との被包括関係に属さない神社というのも意外なほどに多い。リンク先によれば、 ●靖国神社・富岡八幡宮・武蔵御嶽神社・鎌倉宮・鶴岡八幡宮・日光東照宮・気多大社・伏見稲荷大社・梅宮大社・梨木神社・建勲神社・車折神社・出雲大神宮・石切剣箭神社・日前神宮・國懸神宮・淡嶋神社・草戸稲荷神社・金刀比羅宮 などがある。また明治神宮は2004年に神社本庁と被包括関係を解消し、別表神社から離脱したが、2010年8月23日に再び神社本庁と被包括関係になった。 上掲に挙げられている出雲大神宮については、ウィキペディアでは以下のように説明されていた。 ●出雲大社が神社本庁(神社神道)に所属するのに対し、出雲大社教は神社本庁(神社神道)には所属していない。法的に言うと、宗教法人出雲大社が宗教法人神社本庁(神社神道)被包括宗教法人であるのに対し、宗教法人出雲大社教は宗教法人神社本庁の被包括宗教法人ではなく、教派神道に属する単立宗教法人となっている。 なお12月に参拝したことのある金刀比羅宮は蔑ろにされた事を理由として2020年6月に離脱している。その理由はこちらに記されている。このほか、鶴岡八幡宮も理由は明確にしていないものの、2024年3月に離脱を神社本庁に通知しているという。 次に2.の「神道は死後の世界をどう考えているか? 」についてのCopilotに尋ねたところ、以下のような回答をいただいた【要約・改変あり】。
3.の「神道で一番偉い神様は?」についてのCopilotの回答は以下の通りであった【要約・改変あり】。 神道において最も重要な神様の一人として知られるのは、天照大神(あまてらすおおみかみ)です。天照大神は太陽神であり、神道の最高神とされることが多いです。 天照大神については、伊勢神宮、天岩戸など、この私でもある程度のことは存じ上げているが、配偶者が弟のスサノオであったという説は今回初めて知った。ま「誓約が両神の結婚を表しているという解釈」なので、人間の近親相姦には該当しないのかもしれない。 なお、上掲のCopilotの回答に関連して、 ●天照大神がいちばん重要であるという考えは一神教ではありませんか? と尋ねたところ、以下のような回答をいただいた。 面白い視点ですね。神道は多神教であり、多くの神々が存在し、それぞれが異なる役割を持っています。天照大神はその中で特に重要な神様の一人とされていますが、一神教のように唯一の絶対神を信仰するわけではありません。このほか、ウィキペディアには、以下のような記述があった。 明治13年に東京都日比谷の神道事務局に設けられた神宮遥拝所において、神造化三神(天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神)および天照大神の四柱を祀ると決定されたことに対して、出雲派は大国主神も祀るべきだと主張し、伊勢派との間で大きな論争になったが、伊勢派が明治天皇の支持を得たこともあって、出雲派は敗北し、大国主神は祀られないことになった(明治13年の祭神論争)。上掲にある天之御中主神はウィキペディアでは「日本神話における創造神のことであり、神話時代の系譜の中で最初に現れる神で、天地開闢の章に登場する。」、「『古事記』では冒頭の記述で、天地開闢の時に最初に現れた神であるとされている。」というようにきわめて重要な神であるように思われるが、まことに失礼ながら、私はそのような神様がおられるとは知らなかった。加齢により記憶力がますます衰えているなか、読み方を覚えられる自信は全く無い。復古神道では天之御中主神が最高位の究極神とされたようであるが、現在、祀られている神社は少ないようだ。 最後の「神主になるにはどうすればいいか?」についてはCopilotから以下のような回答をいただいた。 神主になるためには、いくつかのステップと要件があります。以下にその一般的な手順を示します:このほかウィキペディアに詳細な解説があるほか、YouTubeでも、 ●神主になるための試験問題! 超難問!? という動画があった。試験問題はかなりの難問であるが、指定参考書を見て答えてもいい試験もあり、また出題範囲が決まっているので模範解答を丸暗記しておけば比較的簡単に合格できるかもしれない。 なお試験問題の中には、
もう少し一般向けのものとしては神社検定がある。 今回で岡田斗司夫さんのYouTube動画をネタとした連載は終了。次回は、YouTubeでいくつか配信されている年金インタビューについて取り上げる予定。 |