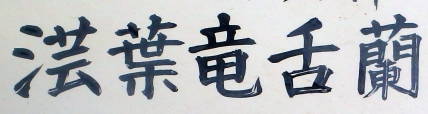【連載】あしたが変わるトリセツショー「新・瞑想」(2)マインドフルネス/うつと不安の違い
昨日に続いて、2024年7月11日に初回放送された、
●#72 さらば!イライラ不安「新・瞑想」のトリセツ
についてメモと感想。
昨日の最後のところで、AI(ChatGPT)は、瞑想の達人たちの共通の見解を以下のようにまとめていた。
●思考や感情に執着せず、今この瞬間にただ気づき、心の本来の静けさへとしなやかに戻っていくプロセス
いっぽう放送のほうでは、瞑想と脳の関係を研究している熊野宏昭さん(早稲田大学)が登場された。ご自身も20年近く瞑想を続けている瞑想研究の第一人者として紹介されていた。熊野さんの御研究や御著書についてはこのWeb日記でも何度か取り上げさせていただいたことがある。ご自身の自己紹介ページから略歴等を抜粋させていただくと以下のようになる【要約・改変あり】。。
- 1960年 石川県生まれ。1985年 東京大学医学部卒。1995年 東京大学博士(医学)取得。
- 医師と心理師双方の世界に身を置いて、患者が主体的に病気を治し健康を維持増進できる医療の実現を目指して、教育・研究・臨床を続けてきた。現在は、マインドフルネスやアクセプタンスを活用する認知・行動療法によって、短期間で大きな効果を上げることを目指した教育・研究を行っている。
- 臨床面では、早稲田大学人間科学学術院心理相談室において相談及び相談補助員の指導に当たるとともに、綾瀬駅前診療所において、パニック障害、軽症うつ病、摂食障害、心身症などを対象に、薬物療法や面接治療に加え、心理師とともに、認知・行動療法、マインドフルネス、アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)などを用いた診療を行っている。
放送で紹介された研究では、まず一般の人の雑念の脳波のデータ、さらに瞑想経験が長い人の脳波が集められ比較された。その結果、瞑想経験が長い人でも一般人と同程度に雑念が浮かんでいることが確認された。
しかし、雑念にハッと気づいてから集中に戻すまでの時間は瞑想経験が長いほど短くなることが分かった。【放送画面によると、瞑想経験時間の長さの順位と復帰時間平均値の順位のあいだの順位相関係数が有意であることが確認された。】 つまり、瞑想経験が長い人ほど、雑念から素早く現実に戻れるということになる。前回引用した4人の達人の言葉の中にも「竹のようにしなやかに戻る」、「我に返ってくる」、「泡が消えて水に戻る」というように「戻る」という意味が含まれていた。以上をふまえて放送では、瞑想の極意を以下のように定式化した。
●雑念に気づき目の前のことに意識を戻す
この「新・瞑想法」がまさに『マインドフルネス』であり、「仏教の瞑想法をもとに誰でも取り組めるプログラムとして科学的に開発されたもの」ということになる。
ここまでのところで生じる疑問は、なぜ「雑念に気づき意識を戻す」のがいいのか?という点にある。これについての解説は以下の通り【要約・改変あり】。
- そもそも脳には雑念が浮かびやすい性質がある。
- 仕事上のストレスがあると現実に起こっていないような妄想を含めて頭がいっぱいになる。この状態が長く続くと、うつや不眠の原因にもなる。
- じっさい集中している時と雑念が浮かんでいる時の脳画像を比較すると雑念中のほうが脳が活発になっている。梅干しという雑念から唾液が出るように【=条件反射】、失敗というような嫌な言葉を見ただけで(実際には失敗していないのに)その言葉から連想される嫌な出来事を現実に体験したかのように感じてしまう。
以上から、嫌な雑念が浮かぶこと自体は避けられないとしても、その言葉から派生する嫌な出来事を思い浮かべる前に速やかに現実に意識を戻す訓練を行うことは有用であると考えることができる。
なお、以上は、さまざまな不安の原因は雑念から派生しているという前提に立っている。上掲では、妄想のような雑念で頭がいっぱいになる状態が長く続くと、うつや不眠の原因にもなると指摘されていたが、うつ状態というのは必ずしも妄想がいっぱいになった状態ではなく、何もしたくないほどに気分が落ち込んだ状態のことを言う。念のためChatGPTに、うつと不安の違いについて説明してもらったところ以下のような回答をいただいた。
うつ(鬱)と不安は、どちらも心の不調を表す言葉ですが、**症状・感情・体験の質が異なる**点がいくつかあります。以下に主な違いをわかりやすく整理します。
- **感情の違い**
| うつ(鬱) | 不安 |
| ------- | -------------------- | -------------------- |
| 主な感情 | 抑うつ(気分が落ち込む、無力感、悲しみ) | 緊張・心配・恐れ |
| 体験される気分 | 「何もしたくない」「もうだめだ」 | 「どうしよう」「何か悪いことが起きそう」 |
- **身体的な症状の違い**
| 症状 | うつ | 不安 |
| ----- | ---------- | ------------------------ |
| 体の動き | 活動の低下、無気力 | そわそわ、落ち着かない |
| 睡眠 | 眠れない、または過眠 | 入眠困難、中途覚醒、悪夢 |
| 食欲 | 食欲減退または過食 | 食欲の低下が多いが緊張による変動も |
| 身体の感覚 | 疲労感、身体が重い | 動悸、発汗、震え、息苦しさなど交感神経の過剰反応 |
- **思考の特徴**
| 特徴 | うつ | 不安 |
| ----- | ---------------------------- | --------------------------- |
| 思考の内容 | 「自分には価値がない」「何をしても無駄だ」など否定的思考 | 「最悪の事態が起きる」「失敗するかも」など未来への心配 |
| 思考の方向 | 過去への後悔・自己否定 | 未来への過剰な心配 |
- **行動の変化**
| うつ | 不安 |
| ---------------- | ---------------------------- |
| 行動量が減る、外出や趣味をやめる | 落ち着きがなくなる、確認行動が増える(例:鍵の確認など) |
- **診断上の分類**
- * **うつ病(うつ状態)**:
* 「気分が落ち込む」「何も楽しくない」状態が2週間以上続く
* 興味や意欲の喪失、自責感などが強く、重度になると自殺念慮も
- * **不安障害(例:全般性不安障害、パニック障害、社交不安など)**:
* 過剰な心配や恐怖が6か月以上続く(状況により異なる)
* 身体の過覚醒(動悸・過呼吸)を伴うことも多い
- **共通点と重なり**
* 実際には「**うつ+不安**」のように**両方が同時に出現する**ことがよくあります。
* たとえば、うつの人が将来への不安を強く感じたり、不安障害の人が自己否定で落ち込んだりすることも。
- ## ?? まとめ:一言で言うなら
* **うつ**:希望を失い、すべてが無意味に思える気持ち
* **不安**:何か悪いことが起きそうで落ち着かない気持ち
医学の専門的なことについては全く分からないが、以上の特徴を比較すると、瞑想が有効となるのは不安障害、いっぽう「うつ」はそもそも雑念が生じなくてもその状態が続くことからみて、瞑想では改善できない部分が多いように思われる。
じっさい、うつでは例えば呼吸に注意を集中するといってもそのような行為さえ無意味に感じるだろうし、派生すると悪循環をもたらすような雑念は何も浮かんで来ないかもしれない【「何も楽しくない」とか「興味や意欲の喪失」というのは状態であって当事者の雑念ではない】。
ではどうすればいいのか? ということになるが、私のような者がここで何かを書くと、それが間違っていたり誤解されたりした時にとんでもないことになりかねないので、ここでは何も記さないことにさせていただく。
不定期ながら次回に続く。
|